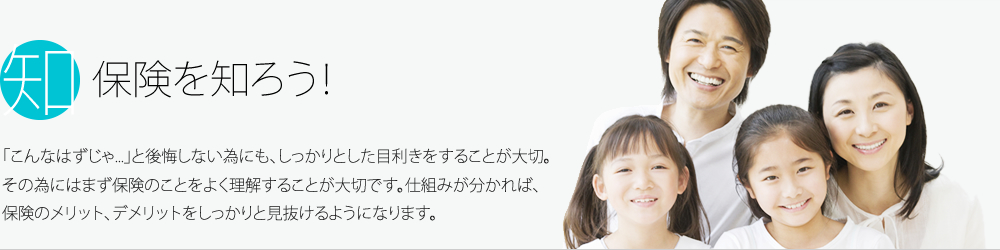
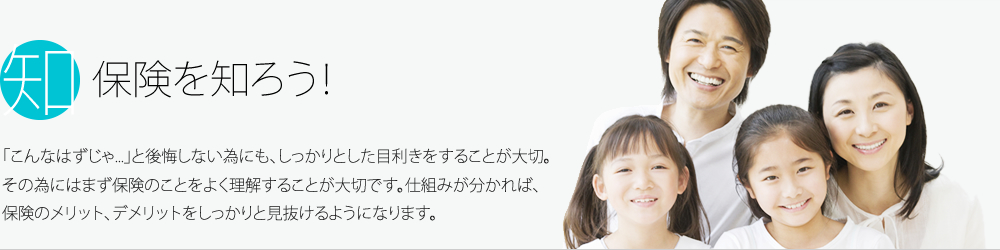
保険は、万が一のリスクに備える商品ですが、営業の方に言われるままにそのリスクの全てを保険で準備する必要はありません。
私達のまわりには、高額療養費制度などの社会保障制度があります。また、会社などにお勤めの方で、手厚い企業の福利厚生がある場合もあります。
このように、保険だけに頼らなくても、「いざという時に、自分をサポートしてくれるもの」はたくさんあります。そうしたサポートがあった上で、自分で対応できる範囲を超えてしまうものだけをカバーするのが、賢い保険の利用方法です。
その方のステータスや周りの環境などのライフプランによって、考えられるリスクは大きく異なります。また、自分だけだと気づきにくいリスクも多くありますので、家族や周りの方に聞いてみたり、専門のファイナンシャルプランナーに相談して、一度書き出してみましょう。
ライフプランとは、時間軸においての将来の生活設計のことを言います。
例えば「結婚」「子供の誕生・進学」「転職」「退職」「住宅購入」「親の介護」「相続」「老後の生活」など、人生の転機におけるさまざまなイベントを思い描き、準備・計画をすることが、ライフプランの設計になります。
こうしたライフプランを設計することによって漠然と考えていた自身と家族のライフイベントを再確認できるとともに目標を具体的に数値化できるようになります。
また一方で、予期せぬ事態が発生した場合に自身と家族が被る経済的損失を想定するプランニングの作成も必要となります。
こうした経済的損失を想定するプランニングをリスクマネジメントといいます。ライフプランニングとリスクマネジメントは表裏一体の関係にあり、ライフプランを実現しようとするときにリスクマネジメントも不可欠なものとなります。
万が一病気になってしまったり、事故にあってしまったら、いくらぐらい必要なのかを可能な限り具体的に算出します。ポイントは、今だけでなく「1年後は? 10年後は?」といった将来を見据えた時系列で考えることです。
特に、社会保障制度や、企業にお勤めの方は会社の福利厚生制度など、よく調べてみると大きな保障(補償)をしてくれるものはたくさんあります。
例えば、一軒家をローンで買った方が、ご自身に万が一のことがあった時にローン残高が0になる団体信用生命保険契約を結ばれている場合なども、いざという時に補助してくれるものとして捉え、必要額から差し引くことが出来ます。
このように、周りで補助してくれるものは差し引いて考えて、準備をすることが大切です。
公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
高額療養費制度では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
貯金で準備できるものまで保険で準備する必要は全くありません。自分だけでは準備できないリスクへの対策として、保険の利用を考えましょう。
保険は、自己責任の商品です。保険屋さんに言われるままなんとなく契約するのではなく、自分のリスクを把握して、目的を持った保険選びをすることが、とても大事です。