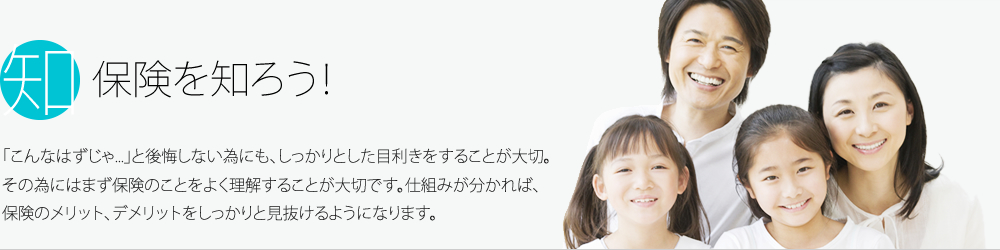
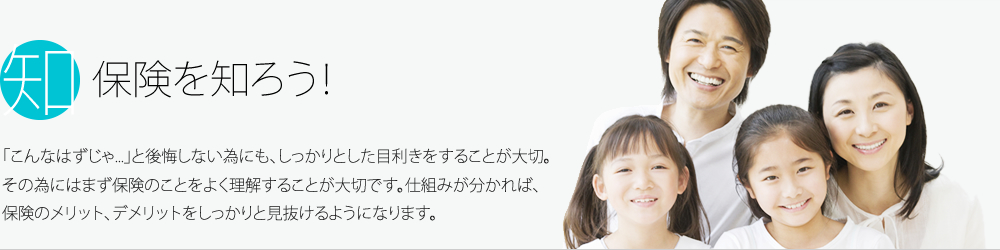
男性が60歳までに死亡する確率は、厚生労働省 平成25年簡易生命表によると、約8%となっています。意外と多いなと感じるでしょうか。ただしこの数字は、元々体の弱い方や、健康ではない人も多く含まれている全人口からの約8%です。
「生命保険に加入している(できる)男性」で60歳までに死亡する確率はもっともっと低いでしょう。なぜなら、生命保険に加入するには保険会社の審査や医師の診断を受ける必要があり、一定以上の健康な方しか加入できないからです。
なお、女性はさらに死亡率が低く、厚生労働省 平成25年簡易生命表によると、約4%となっています。また、「生命保険に加入している(できる)女性」で60歳までに死亡する確率はもっともっと低いでしょう。
ただし、小さいながらも死亡するリスクがある以上、「万が一」のうちの一人になってしまった時のことは想定しておかなければなりません。
それは、残された家族の金銭面での負担を軽減するためにあります。
社会人になったり、ご結婚されたり、お子様の誕生のタイミングで死亡保険を考える方も多いのではないでしょうか。その他にも、転職や、引越し、1軒家の購入、自身の葬式代のためや、相続税対策のために考える方もいらっしゃるでしょう。死亡保険は、自分のためというよりは、残された家族のために考える保険です。
必要となる保障額は、加入目的ごとに大きく異なります。
大事なのは、実際にいくら必要なのかをしっかり数字に置きかえることです。
例えば、1軒家を購入してローンを組んだ場合、万が一の時に遺族がローンを返せるかどうかが心配ですよね。これを死亡保険で準備しようとした場合には、必要な保障額はローン残額です。なので、ローン残額に合わせた保険金額や保険期間の商品を検討することが大切です。
入りすぎても、もったいないですが、少なすぎても万が一の時に困ってしまいますので、多少面倒でも正確な保障額の割り出しは行った方が賢明です。同様に他の目的に対しても、必要保障額を考えるのが第一歩です。
例えば、企業にお勤めで厚生年金に長く加入しているご主人に、今すぐ万が一のことがあった場合、残された遺族の生活資金や教育資金を考えると3,000万円が必要だと算出したとします。
じゃあ、3,000万円の死亡保険に入る必要があるのかというと、実はそうではありません。実際に自分で準備しなければいけない金額は、もっと少なくてすむ場合がほとんどです。何故なら、公的な遺族年金や、会社の福利厚生制度からの支給を考えることが出来るからです。
「全て死亡保険でまかなう」のではなくて、あくまで公的な保障で足りない部分を補うという考え方が大切です。
公的遺族年金とは3種類ある公的年金、「国民年金」「厚生年金」「共済年金」に加入中の人・加入していた人が亡くなったときに遺族に支給されるものです。公的遺族年金の仕組みや算出方法については、日本年金機構のホームページでご確認ください。